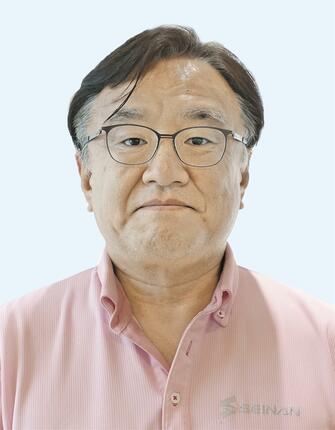日本鉄リサイクル工業会の国際ネットワーク委員会で2012年から12年間の長きにわたって委員長を務めてきた安東元吉氏(青南商事社長)。同委員会の歩みを良く知る同氏に発足時の時代背景や、活動の思い出などを聞いた。
――まずは、国際ネットワーク委員会が発足した当時の時代背景について。
「私は委員会の創設メンバーではないが、発足後の比較的早い段階で委員となった。当時は鉄スクラップが国際商品となった時期に当たる。そのため、海外と国際マーケットに関する情報収集が可能な関係を構築する必要性が高まっていた。また、日本からの鉄スクラップ輸出量が増えていく中、国際マーケットで日本の鉄スクラップ業の存在感を高めていかなくてはならないという時代だった」
「当時、国際マーケット情報は基本的に商社を経由して入ってきていたが、海外と直接、情報交換する関係をもった鉄スクラップ業者は限られていた。そこで、国際ネットワーク委員会が国際的な会議に参加し、講演を行うことで日本の鉄スクラップ業のプレゼンスを向上。それによって海外の団体などと人間関係を構築しやすくなっていった」
――海外情報の入手に関しても、大きく代が変化した。
「情報化社会の進展によって、ネットを経由してさまざまな国際マーケット情報の入手が可能となっている。ビデオ会議システムで直接、海外と会話することもできる。業界内に国際感覚のある人材も増えた。国際ネットワーク委員会が窓口になって情報収集するニーズは発足当時ほど大きくはないのかもしれない」
――国際ネットワーク委員会の成果や、活動の思い出を。
「委員会の成果は工業会の会員の皆さんが評価するべきもの。ただ、私が最も強く思い出に残っているのが、委員長に就任して初めて迎えた2013年の国際鉄リサイクルフォーラム。東南アジア鉄鋼協会(SEAISI)が初参加し、ベトナム市場を紹介したこと、また、その後のフォーラムではバングラデシュの鉄鋼メーカーを招待し、インドを含めた南西アジア市場の可能性をいち早く紹介できた。さらに、当時ニーズが高まり始めていた共同輸出の代表例として関東鉄源協同組合の取り組みを紹介させていただいた。最近は韓国や中国などでも鉄スクラップ業界団体が国際フォーラムの開催を始めている。国際ネットワーク委員会の活動がアジア各国の鉄スクラップ業の活性化につながったのであればうれしい」
「委員からは非常にやりがいのある活動だったという感想を聞いている。これは私も全く同感だ。国際ネットワーク委員会では毎回、非常に中身の濃い、熱い議論が行われてきた。特に国際鉄リサイクルフォーラムに関しては、次回はさらに良い内容にしようと、年々ハードルを上げて準備が進められた。特に全国大会が開催される日本各地の良さを海外からの参加者に楽しんでもらえるよう力を尽くした。ベジタリアン用の食事など個々のゲストの文化を尊重して準備することにも気を配った。こうした努力は、翌年のフォーラムで海外ゲストの講演内容が良くなるという形で実を結んだと思う。国際ネットワーク委員会の活動は苦労も多いが、自らを磨く上では非常に良い機会になった」